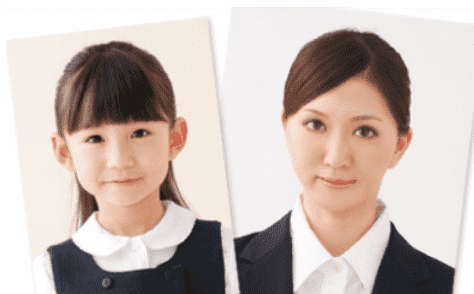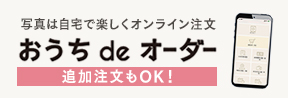お食い初めはいつ・どこで行う?日程の計算方法、やり方をわかりやすく解説
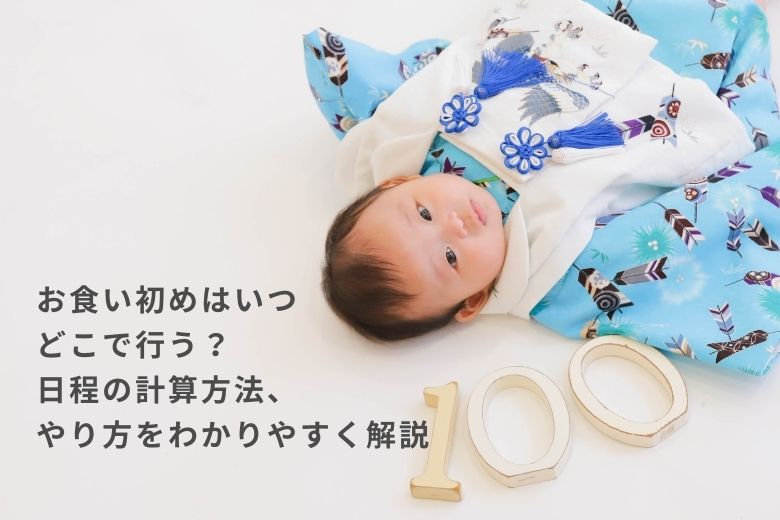
お食い初めは、赤ちゃんが一生食べ物に困らないようにという願いを込めて行われる伝統的な儀式です。初めての子育てでは「お食い初めをいつ行うの?」「どこで準備すればいい?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。本記事では、お食い初めの時期や場所、おすすめの時間や、具体的な準備方法、そして手順についてわかりやすく解説します。ぜひ、赤ちゃんとの大切な節目をより素敵なものにするための参考にしてください。
目次
そもそも、お食い初め(百日祝い)とは何?
お食い初めとは、赤ちゃんが生後100日を迎えた頃に行う日本の伝統的な儀式です。「一生食べ物に困らないように」という願いを込めて、初めての食事をする真似をする行事で、「百日祝い(ももかいわい)」とも呼ばれます。実際には赤ちゃんはまだ離乳食を始めていない時期のため、食べるふりをするのが一般的です。この儀式は、家族や親しい人々とともに赤ちゃんの成長を喜び、絆を深める大切なイベントとして受け継がれてきました。
お食い初めはいつ行う?
お食い初めは、赤ちゃんが生後100日目を迎える頃に行うのが一般的です。しかし、家庭の都合や日取りの良し悪しを考慮し、100日を少し過ぎた時期に行うこともあります。
百日の数え方
百日は赤ちゃんが生まれた日を1日目として数えます。例えば、2024年1月1日に生まれた赤ちゃんの場合、2024年4月9日が100日目となります。ただし、厳密に100日にこだわる必要はありません。家族が集まりやすい週末や、祖父母などのスケジュールに合わせて行う方も多いです。また、大安など縁起の良い日を選ぶのも人気の方法です。
地域や風習による違い
地域によっては120日目に行う場合もあります。これは、赤ちゃんの体調や家族の予定に柔軟に対応するための配慮です。重要なのは、赤ちゃんの成長を祝う気持ちを持つことなので、日程についてはあまり神経質になりすぎず、家族が楽しく参加できるタイミングを選ぶと良いでしょう。
相性の良い六曜は?
お食い初めの日取りを決める際、六曜を参考にすることもあります。
六曜には「大安」「友引」「先勝」「先負」「赤口」「仏滅」の6種類があり、特に「大安」は何事にも縁起が良い日とされ、お祝いごとに適しています。
また、「友引」も「幸せのお裾分け」の意味があり、お食い初めに向いているとされています。ただし、六曜にこだわりすぎる必要はなく、100日前後で家族の都合が良い日を優先して決めるのが最も大切です。
実施する時間帯のおすすめは?
お食い初めを行う時間帯は特に決まりがなく、家族にとって都合の良いタイミングを優先するのが一番です。特に、赤ちゃんの授乳タイミングやお昼寝の時間を考慮し、できるだけ機嫌の良い時間帯を選ぶとスムーズに進みます。以下、時間帯ごとのメリットを紹介します。
午前中(10時~11時頃)
・ 赤ちゃんが朝の機嫌が良く、泣かずに儀式を進めやすい
・ 昼食前に終えられるため、家族が午後の予定を立てやすい
・ お店を利用する場合、ランチの混雑を避けやすい
昼頃(12時~13時頃)
・ 遠方から親戚を招く場合に時間調整しやすい
・ 食事と一緒に進めやすく、儀式後にそのまま家族で会食できる
・ お店を利用する場合、ランチのピークタイムと重なる可能性がある
午後(14時~15時頃)
・ ランチ後の落ち着いた時間帯で、お店の混雑を避けやすい
・ 午前中の家事や準備をゆっくり進められる
・ ただし、赤ちゃんのお昼寝時間と重なることが多いため注意が必要
どの時間帯を選ぶにしても、最も大切なのは赤ちゃんと両親の負担を減らし、ゆったりとした気持ちでお祝いできることです。授乳タイミングやお昼寝時間を考慮しながら、無理のない時間を選びましょう。
お食い初めを行う場所
お食い初めは、自宅で行う場合もあれば、外食や料亭、ホテルなどを利用する場合もあります。それぞれの場所にメリットがあり、家庭の状況や希望に合わせて選びましょう。
自宅でお食い初めを行う
自宅でお食い初めを行う場合は、リラックスした雰囲気で家族団らんのひとときを楽しめます。自分で料理を準備することで、赤ちゃんへの想いを込めた特別な食事を用意することができ、費用を抑えることもできる点が魅力です。また、お食い初め膳の宅配サービスを利用するのも便利です。本格的なお料を自宅で楽しむことができ、歯固めの石がついているセットもあります。
レストランや料亭で行う
外食でお食い初めを行う場合は、プロが準備した本格的なお食い初め膳を楽しむことができます。特に料亭や和食レストランでは、儀式に必要な鯛や赤飯などの料理が用意されており、家族が手軽に参加できます。また、準備や片付けの手間を省けるため、忙しい方におすすめです。
お食い初めで準備するメニュー例
お食い初めでは、赤ちゃんが「一生食べ物に困らない」ことを祈るために縁起の良い料理を用意します。以下は代表的なメニュー例です。

鯛の塩焼き
鯛の塩焼きは、お食い初めの主役となる料理で、「めでたい」という言葉に通じる縁起物です。鯛は見た目の華やかさや風味の良さだけでなく、赤ちゃんの健やかな成長や将来の幸運を祈る象徴的な食材です。塩焼きにすることで、鯛本来の美味しさを引き立て、祝いの席を彩ります。焼き上げる際には尾頭付きで準備し、赤ちゃんを中心とした家族の絆を感じられる一品となります。

赤飯
赤飯は、お祝いの席には欠かせない料理で、もち米を使った縁起の良い食べ物です。その赤い色には魔除けの意味があり、赤ちゃんが健康に育つことを願う想いが込められています。小豆やささげを用いることで独特の風味が加わり、特別感を演出します。また、赤飯は昔からお祝い事に供される定番料理であり、親族みんなが赤ちゃんの成長を祝う気持ちを共有する象徴的な存在です。

蛤の吸い物
蛤のお吸い物は、「貝殻がぴったりと合う」という特性から、調和や良縁を象徴する料理です。蛤は祝い事にふさわしい高級感のある食材で、澄んだだしが清らかさを演出します。昆布や鰹節で丁寧に取っただしを使い、味付けは控えめに仕上げて蛤の旨みを引き立てます。三つ葉や手毬麩を添えることで彩りを加え、お吸い物全体が赤ちゃんの健やかな未来と家庭の円満を願う一品となります。

お食い初めのやり方とは?
お食い初めは、料理を赤ちゃんの口元に運び、食べる真似をする儀式です。必要なものとして食器類や歯固めの石、お祝い膳を用意します。また、食べさせる人や順番などしきたりがありますので具体的な手順について解説します。
食べさせる人は
お食い初めの料理を食べさせる真似をする人の事を「養い親」と呼ばれます。招待した近親者の中から最年長の人が行うのが一般的でしたが、近年では祖父母にお願いすることが多いようです。都合が合わない場合はパパやママが行っても問題ありません。赤ちゃんが女の子なら女性が行い、男の子なら男性が努めます。正式なやり方にこだわらず、家族みんなで交互に食べさせてあげるのも良い思い出になります。
一般的な順番
地域により違いがありますが、お食い初めでは料理を以下の順番で食べさせる真似を行い、それを3回繰り返したのちに「歯固めの儀式」を行います。
料理を口元に運ぶ順番は以下の通りです
ご飯→お吸い物→ご飯→お魚→ご飯→お吸い物
赤ちゃんはまだ食べることができませんので、上記の手順で口元に運んで食べる真似をしょう。
料理が他にある場合の順番
上記以外に煮物や香の物がある場合、地域にもよりますが、2回目や3回目の途中でご飯の次に食べる真似をします。以下は一例です。
ご飯→お吸い物→ご飯→お魚→ご飯→お吸い物
→ご飯→お吸い物→ご飯→煮物→ご飯→お吸い物
→ご飯→お吸い物→ご飯→香の物→ご飯→お吸い物
歯固めの儀式
この儀式には「丈夫な歯が生えますように」という願いが込められています。歯固め用の石にお箸を軽くあて、願いを込めながらお箸を赤ちゃんの歯茎に軽く触れさせます。石を赤ちゃんの歯茎に直接あてたり、かませたりすると誤飲などの恐れがあるので避けましょう。石の代わりにタコや栗などを使う地域もあるようです。
儀式が終わった後はお料理を参加者みなさんで美味しくいただきます。儀式で赤ちゃんが嫌がる場合は無理をせず、楽しみながらお祝いしましょう。

お食い初め(百日祝い)の記念写真撮影はスタジオキャラットへ
お食い初めは、赤ちゃんの成長をお祝いする一生に一度のイベントです。この特別な瞬間を写真に残してみませんか?スタジオキャラットでは、プロのカメラマンが赤ちゃんの自然な笑顔を引き出し、記念写真を美しく仕上げます。さらに、お食い初め用の衣装や小道具も豊富に揃っていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
スタジオキャラットのお食い初め(百日祝い)プランはこちら
まとめ
お食い初めは、赤ちゃんの健やかな成長を願い、家族の絆を深める大切な行事です。時期や場所、準備するメニューについてポイントを押さえれば、思い出に残る素敵なセレモニーが実現します。赤ちゃんとの大切な時間をより特別なものにするための参考にしてください。また、あまり形式にこだわりすぎず、それぞれのご家庭にあったスタイルでお食い初めを楽しんでください。そして、その瞬間を記念写真として残したい方は、スタジオキャラットのサービスもぜひご利用ください。
再編集:2025年3月24日