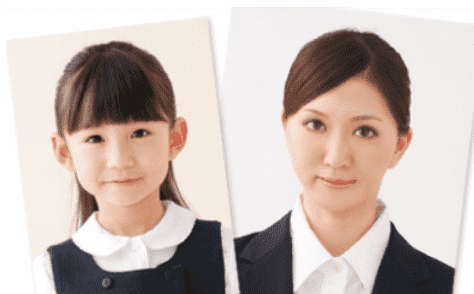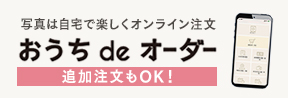お宮参り両家トラブル回避!参加者と抱っこ役を事前に話し合う注意点

お宮参りは赤ちゃんの健やかな成長を祈る大切な行事。
しかし、両家の考え方や慣習の違いから「主導権争い」や「費用負担」「抱っこ役」などで思わぬトラブルに発展することもあります。特に初めてのお宮参りでは、何が正解か分からず悩むママ・パパも多いですよね。
本記事では、実際によくある「お宮参り両家トラブル」とその回避法をわかりやすく解説します。家族みんなが笑顔でお祝いできるよう、事前準備のポイントをぜひ参考にしてください。
お宮参り両家トラブルの主な原因
お宮参りは赤ちゃんを中心としたお祝いの場ですが、両家の価値観の違いが表面化しやすいイベントでもあります。以下のような5つの原因でトラブルが起こることが多いです。
① 主導権を巡る意見の対立:父方・母方のどちらが仕切るかで揉めるケース。
② 費用負担への認識のズレ:初穂料や会食費の分担を巡る誤解。
③ 赤ちゃんを抱っこする人選び:伝統的なしきたりと現代の考え方の違い。
④ 日程調整での価値観の違い:生後1ヶ月厳守派と体調優先派の意見対立。
⑤ 参拝する神社選びでの揉め事:地元神社か夫婦の希望神社かで意見が分かれる。
これらの原因を理解しておくことで、トラブルを事前に回避しやすくなります。
①主導権を巡る意見の対立
お宮参りでは、昔から「父方の行事」と考える地域も多く、祖父母の中には「うちはこうしてきたから」と当然のように父方が主導すると思っている方もいます。
一方、現代では「両家平等」や「夫婦中心で進めたい」という考え方が主流になりつつあります。
例えば、母方の祖母が「うちの娘が出産したのだから、私も主役の一人」と考えているのに対し、父方の祖母が「お宮参りは父方の家の行事」と譲らないケースも。どちらも悪気がないだけに、ちょっとした一言で雰囲気がピリつくこともあります。
こうした対立を防ぐには、「夫婦が主導して決める」姿勢を明確にすることが大切です。例えば「私たち夫婦で段取りしますので、ご都合を教えてくださいね」と最初に伝えておくと、両家の温度差をやわらげることができます。
主導権をどちらにするかではなく、「赤ちゃんのために、みんなで気持ちよくお祝いする」という目的を共有することがトラブル回避の第一歩です。
②費用負担への認識のズレ
お宮参りでは「誰が、どの費用を負担するのか」があいまいなまま進めてしまい、あとで気まずい思いをするケースが少なくありません。
主な費用は
「初穂料(はつほりょう:神社へ納めるお礼)」
「衣装代」
「会食費」です。
昔は父方の祖父母がすべて負担する慣習もありましたが、今は「それぞれの家庭で分担する」「夫婦が自分たちで支払う」というスタイルも増えています。
例えば、父方が「初穂料はこちらで出すね」と言ったのに、母方が「会食費はこちらが負担します」と申し出た結果、「うちも払うつもりだったのに…」と気を悪くするなど、好意のすれ違いが起きやすいのです。
解決策としては、事前に夫婦で費用の分担方針を決めておくこと。そのうえで両家に「今回は私たちで負担します」「初穂料だけお願いできれば助かります」など、明確に伝えるとトラブルを防げます。金額の話は言いづらいものですが、あいまいにすると後々の誤解につながるため、早めの共有が安心です。
③赤ちゃんを抱っこする人選び
お宮参りで最も揉めやすいのが、「赤ちゃんを誰が抱っこするか」という問題です。
昔ながらの風習では、「お宮参りでは父方の祖母が赤ちゃんを抱く」とされてきました。理由は「産後の穢れの期間」という古いしきたりに基づくもので、母親ではなく父方の祖母が抱くのが一般的だったのです。
しかし現在では、ママの体調が落ち着いていれば、両親が抱っこして参拝することも多く、写真スタジオでもご希望に合わせて、しきたりを気にせず撮影することが増えています。
そこで問題になるのが、「昔ながらのしきたりを大切にしたい祖母」と「自分で抱っこしたいママ」の気持ちのズレ。祖母に悪気がなくても、「私が抱くのが普通よ」と言われるとママが戸惑ってしまいます。
解決のコツは、事前に夫婦で方針を決めて伝えること。
「今は母親が抱っこすることも多いようですし、ママの希望を優先したいです」と丁寧に説明すれば、理解してもらいやすくなります。写真撮影時には祖母にも抱っこしてもらうなど、両者の気持ちを尊重する形にすると円満です。
④日程調整での価値観の違い
お宮参りは「生後1か月頃に行う」という風習がありますが、現代では「赤ちゃんとママの体調を最優先にしたい」と考える家庭が増えています。ここで意見が分かれると、両家トラブルの火種に。
特に祖父母世代は、「1か月を過ぎるとご利益が薄れる」といった昔の考え方を重んじる傾向があり、「きっちり1か月で行くべき」と主張することも。
一方、現代のママ・パパは「まだ外出が不安」「暑さ・寒さが心配だから時期をずらしたい」と考える場合もあります。
どちらも赤ちゃんを思っての気持ちなので、否定せずに理由を丁寧に伝えることが大切です。
「お天気が落ち着いてから行きたい」「赤ちゃんの予防接種が終わってからにしたい」など、具体的に説明すれば納得してもらいやすくなります。お宮参りの日程に正解はありません。大切なのは「みんなが安心して祝えるタイミング」を選ぶことです。
⑤参拝する神社選びでの揉め事
お宮参りでは「どの神社に行くか」も意外とトラブルになりやすいポイントです。
昔は「産土神(うぶすながみ)=生まれた土地を守る神様」へのお参りが一般的でしたが、最近は「安産祈願をした神社」「夫婦で好きな神社」など、自由に選ぶ家庭も増えています。
しかし、ここで「うちは地元の氏神様にお参りするものだ」と考える祖父母と、「せっかくだから雰囲気の良い神社で写真も撮りたい」と思う夫婦の意見がぶつかることも。特に両家が離れている場合、「どちらの地域に行くか」で揉めるケースも少なくありません。
対策としては、両家の希望を一度すべて出してから話し合うこと。
その上で「移動の負担」や「赤ちゃんの体調」を優先して選ぶと納得されやすいです。どうしても決まらない場合は、「参拝は地元で、写真撮影は別のスタジオで」と分けるのもおすすめです。
お宮参りのマナーの変化によるトラブル

お宮参りは古くから続く伝統行事ですが、時代とともにマナーや考え方も変化しています。
この“世代間ギャップ”が原因で、両家トラブルにつながるケースが増えています。
特に次の4つのポイントで価値観がぶつかりやすいです。
① お参り時期への考え方の変化:生後1か月厳守派と体調優先派の違い。
② 参加者の範囲に対する世代間ギャップ:父方中心か、両家で行うかの認識差。
③ 服装選びの自由度への温度差:正装派とカジュアル派の価値観の違い。
④ 参拝スタイルへの価値観の相違:しきたり重視か、家族イベント重視か。
どれも「赤ちゃんを祝いたい」という気持ちは同じですが、時代によって正解が異なるため、丁寧な話し合いが必要です。
①お参り時期への考え方の変化
昔は多くの知育では「男の子は生後31日目、女の子は32日目」と日程が厳密に決められていました。そのため祖父母世代の中には、「お宮参りは1か月ぴったりに行うもの」と信じて疑わない方も多いです。
しかし現代では、出産方法やママの回復具合、赤ちゃんの発育状態もさまざまで、1か月経っても外出が難しいことも珍しくありません。さらに季節によっては、真夏や真冬に外出させるのは避けたいという声も多いです。
このように「昔の決まりを守りたい祖父母」と「体調を優先したいパパママ」の間に温度差が生まれがちです。
解決のコツは、医師の意見や赤ちゃんの健康状態を根拠に伝えること。
「先生から外出はもう少し先が安心と言われました」など、専門家の言葉を交えると納得してもらいやすくなります。
お宮参りは「時期」よりも「赤ちゃんが無事に育っていることを感謝する行事」。無理のないスケジュールで行うのが現代のスタイルです。
②参加者の範囲に対する世代間ギャップ
お宮参りは、かつて「父方の行事」とされていたため、父方の祖父母だけが参加するのが一般的でした。母方は衣装やお祝いを贈るだけで当日は不参加、という時代もありました。
しかし今では、出産や育児を母方の実家で支えられている家庭も多く、「両家そろってお祝いしたい」と考えるママパパが多数派です。
この変化が、祖父母世代にはなかなか受け入れられないこともあり、「昔は父方だけだった」「母方も呼ぶの?」という戸惑いが生まれることがあります。
そんなときは、「両家で赤ちゃんを一緒にお祝いできたらうれしい」と前向きに伝えるのがおすすめ。
どちらかの家に偏るとトラブルになりやすいため、両家を平等に扱う姿勢が大切です。
また、人数が多いと移動や会食の調整も大変なので、あらかじめ「参拝だけ両家で、会食は別日」など、柔軟に対応できる形を話し合うのも良い方法です。
④参拝スタイルへの価値観の相違
お宮参りはもともと「神様に感謝と祈りを捧げる宗教的行事」でしたが、現代では「家族の記念日」として楽しむ家庭も増えています。
この“お宮参りの目的”に対する認識の違いが、両家トラブルにつながることもあります。
祖父母世代は「正式なご祈祷を受け、厳かに行うべき」と考える傾向が強い一方で、若い世代は「簡単にお参りして、写真を中心に残したい」とカジュアルにとらえる場合もあります。
どちらが正しいということではなく、目的の重きをどこに置くかの違いです。
トラブルを防ぐには、事前に参拝方法を共有しておくこと。
「ご祈祷を受ける予定」「参拝だけで済ませる」「写真撮影をメインにする」などをあらかじめ説明しておくと安心です。
また、祖父母に「ご祈祷の時間が長いと赤ちゃんがぐずるかもしれないので、短めにしたい」と伝えるなど、赤ちゃんを理由に柔らかく説明すると、角を立てずに理解してもらいやすくなります。
祖父母と話し合っておきたいポイント

お宮参りで両家トラブルを避けるためには、事前の話し合いが一番のカギです。
特に、次の4つのポイントを前もって確認しておくと、当日スムーズに進められます。
① 参加者の範囲:誰を呼ぶか、どこまでの親族が参加するかを明確にする。
② 当日の役割分担:抱っこ役、写真撮影、進行などを事前に決めておく。
③ 写真撮影の希望:抱っこ順や撮影場所、写真館の利用などを調整する。
④ 食事会の内容:会食の有無、場所、費用の分担方法を事前に話し合う。
この4点を整理しておけば、両家の意見のズレや当日の混乱を防ぐことができます。
①参加者の範囲
お宮参りは本来「家族行事」ですが、どこまでの親族を呼ぶかで意見が分かれることがあります。
昔は「父方の祖父母と両親、赤ちゃん」の少人数が一般的でしたが、今では「母方の祖父母」や「兄弟姉妹」も参加する家庭が増えています。
ただし、あまり人数が多いと移動や写真撮影が大変になり、ママや赤ちゃんに負担がかかることも。
そのため、基本は両家の祖父母までを目安にするのがおすすめです。
呼ばない親族がいる場合は、「今回は少人数でお参りを予定しています」など、やわらかい言い回しで伝えると角が立ちません。
また、祖父母に「両家一緒で参加したい」と伝えるときは、「せっかくなので、皆でお祝いできたらうれしい」とポジティブに話すのがコツです。
参加者の範囲を決める際は、人数だけでなく、移動距離・天候・赤ちゃんの月齢なども考慮して、無理のない形を選びましょう。
②当日の役割分担
お宮参り当日は、思っている以上にやることが多く、バタバタしがちです。
参拝の流れ、抱っこ役、写真撮影、荷物の準備、進行などをすべて当日決めようとすると、両家の意見がぶつかってしまうこともあります。
特に「誰が抱っこするか」は、最もトラブルになりやすいポイント。
昔ながらのしきたりでは父方の祖母が抱くとされていましたが、現代ではママやパパが抱くケースも多いです。
そのため、事前に夫婦で抱っこ役を決め、両家に共有しておくことが大切です。
また、写真撮影の際は「赤ちゃんを順番に抱く」「祖父母それぞれで撮る」など、撮影順も話し合っておくとスムーズです。
誰がどの役割を担うのかが明確になっていれば、当日の雰囲気も和やかになります。
「赤ちゃんが主役」という共通認識を持つことで、自然と協力体制が生まれますよ。
③写真撮影の希望
お宮参りの記念に、スタジオや神社境内で写真を撮る家庭がほとんどです。
しかし、ここでも「撮影の順番」や「どんな写真を撮るか」で意見が食い違うことがあります。
たとえば、父方の祖母が「私が抱いた写真を最初に撮ってほしい」と希望したり、母方が「家族3人だけの写真を先に撮りたい」と言ったりするケース。どちらも悪気はないのですが、順番の決め方次第で誤解を生むことも。
そこでおすすめなのが、事前に撮影の流れを決めておくことです。
「最初に家族3人→両家全員→祖父母ごと→個別写真」と順番を整理しておくと、当日がとてもスムーズです。
また、撮影スタジオを利用する場合は、プロのカメラマンに相談するのも◎。経験豊富なスタッフが、両家のバランスを考えながら自然な流れで撮影してくれます。
写真は一生残る宝物。誰もが気持ちよく写れるよう、事前調整がポイントです。
④食事会の内容
お宮参りのあとは会食を行う家庭も多いですが、この「会食の内容・費用・場所」でトラブルが起きることがあります。
祖父母世代は「きちんとした料亭で」「お祝い膳を準備して」と考える一方で、現代のママパパは「カジュアルなランチで十分」「外出は短時間で済ませたい」と思うことも。
また、「誰が支払うのか」を決めないまま当日を迎えると、「え、うちが払うの?」と気まずい空気になることもあります。
そのため、会食をするかどうか・どこで行うか・費用を誰が負担するかを、事前に夫婦で決めておきましょう。
「今回は赤ちゃんの体調を考えて会食はなしにします」「お弁当形式にして自宅で食べます」など、あらかじめ伝えておくことで誤解を防げます。
無理に“形式通り”にしなくても大丈夫。
赤ちゃんとママが安心して過ごせるスタイルこそが、家族にとって一番良いお宮参りです。
両家のトラブルを避けるための対策
お宮参りは一生に一度の大切な行事。
だからこそ、両家の価値観の違いが原因でトラブルになるのは避けたいですよね。
そこで、事前に意識しておきたい6つの具体的な対策をご紹介します。
① 夫婦が主体となって計画する
② 費用分担を事前に明確にする
③ 両親と赤ちゃんのみで行う
④ 両家で別々の日程を組む
⑤ 写真撮影のみに変更する
⑥ 感謝の気持ちを具体的に伝える
どの方法も、無理なく両家に配慮しながら、赤ちゃん中心でお祝いできるコツです。
①夫婦が主体となって計画する
お宮参りの主役は赤ちゃんですが、計画の主導権はパパとママにあるという意識を持つことが大切です。
昔は父方の祖父母が仕切ることが多かったため、今でも「うちが段取りするね」と言われることがあります。悪気はなくても、それがプレッシャーに感じてしまうママも少なくありません。
そんなときは、「私たち夫婦で調整しますね」と柔らかく伝えましょう。
特に、日程・神社・写真館・会食の手配などは夫婦で先に方向性を決めておくと安心です。
また、両家には「赤ちゃんの体調を最優先にしたい」「移動をできるだけ短くしたい」といった理由を添えて説明すると、角が立ちません。
お宮参りは“家族のスタート行事”でもあります。
夫婦が主体となって準備することで、「これからの育児の中心は私たちです」という姿勢を自然に伝えられ、今後の関係性も良好になります。
②費用分担を事前に明確にする
お宮参りで意外と揉めやすいのが「費用の分担」。
初穂料、衣装代、会食費などを誰が支払うかを決めておかないと、後から「え?どちらが払うの?」という微妙な空気になることがあります。
昔は「父方がすべて負担する」こともありましたが、今は「夫婦で」「それぞれの家庭で一部ずつ」など、さまざまなスタイルが主流です。
おすすめは、夫婦で一度すべての費用をリスト化しておくこと。
・神社初穂料(5,000〜10,000円)
・ベビードレス・祝い着レンタル代
・写真撮影代
・会食費
などを一覧にし、「ここは私たちが負担します」「こちらはお願いできると助かります」と明確に伝えましょう。
お金の話はデリケートですが、あいまいにするとトラブルの原因になります。
最初にしっかり話しておけば、感謝の気持ちも伝わりやすく、関係も良好に保てます。
③両親と赤ちゃんのみで行う
近年では、あえて祖父母を招かず「夫婦と赤ちゃんだけでお宮参りをする」家庭も増えています。
このスタイルのメリットは、スケジュール調整が楽で、気疲れが少なく、赤ちゃんのペースで行動できること。撮影も落ち着いてできるため、記念写真が自然な表情になるという声もあります。
一方、デメリットは、祖父母が「招かれなかった」と寂しく感じてしまうこと。
そのため、「今回は赤ちゃんの体調を優先して、夫婦だけで行くことにしました」と、丁寧な説明と感謝の一言を添えることが大切です。
参拝後に写真や動画を送る、「次の機会に一緒にお祝いしよう」と伝えるなど、フォローを忘れなければ問題ありません。
「無理せず、わが家らしい形でお宮参りを迎える」ことこそ、トラブル回避の近道です。
④両家で別々の日程を組む
どうしても両家の意見が合わない場合、それぞれ別日でお宮参りを行うという方法もあります。
父方・母方どちらの希望も尊重でき、スケジュールの都合も合わせやすくなるため、近年増えているスタイルです。
例えば、父方とは「正式なご祈祷を受ける日」、母方とは「写真スタジオで撮影する日」と分けるなど、形を変えて2回行うケースもあります。
両家が別々でも、赤ちゃんにとってはどちらも大切な思い出になります。
この場合は、「皆さんのご都合を考えて、別日でそれぞれお祝いすることにしました」と伝えれば角が立ちません。
ただし、衣装レンタルや撮影スケジュールが重ならないよう、スタジオの予約は早めに行うのがポイントです。
お宮参りを分けることで、両家が気持ちよく参加できるというメリットもあります。
⑤写真撮影のみに変更する
最近では、「神社での参拝はせず、写真撮影だけを行う」という家庭も増えています。
赤ちゃんやママの体調を最優先にでき、天候にも左右されにくいため、現代のライフスタイルに合った選択です。
特に祖父母との日程が合わない場合や、遠方に住んでいる場合にはおすすめ。
「スタジオ撮影でしっかりお祝いの気持ちを形に残したい」と伝えれば、前向きに受け取ってもらえることが多いです。
撮影では、祝い着・ドレス・家族写真などを一度に残せるため、神社参拝に負けない満足感があります。
プロのカメラマンが雰囲気を整えてくれるので、赤ちゃんの笑顔も自然に引き出せます。
大切なのは「どう形に残すか」。
お宮参り=神社参拝という固定観念にとらわれず、「家族で喜びを共有できる形」を選ぶことが、トラブルを避けながら幸せな思い出を作るポイントです。
⑥感謝の気持ちを具体的に伝える
どんなに準備をしても、両家の考え方が完全に一致することは難しいもの。
それでもトラブルを防ぐ最大のコツは、「感謝の気持ちを言葉にすること」です。
「遠くから来てくれてありがとう」「気にかけてくれてうれしい」「お祝いしてもらえて心強い」——
たった一言でも、祖父母の気持ちはぐっと和らぎます。
また、当日のお礼だけでなく、後日写真を送ったり、手書きのメッセージを添えたりするのも効果的です。
形式よりも、「ありがとう」の気持ちが伝わることが大切。
両家との関係づくりは、お宮参りから始まる“これからの家族の絆”です。
小さな気遣いを積み重ねることで、行事のたびに笑顔で集まれる関係を育てていきましょう。
よくある質問
お宮参りは両家で行くべきですか?
必ずしも両家で行う必要はありません。
昔は父方中心で行うのが一般的でしたが、今では「夫婦と赤ちゃんだけ」「両家合同」など、家庭によってさまざまです。
大切なのは形式ではなく、赤ちゃんと家族が気持ちよくお祝いできる形を選ぶこと。両家トラブルを避けるためにも、事前の話し合いを忘れずに。
お宮参りはどちらの親がするのですか?
かつては「父方の祖母が抱っこして参拝する」という風習が一般的でした。
しかし現代では、ママやパパが抱くことも多く、どちらの親が主導するかは家庭の考え方次第です。
夫婦が主体で決めるのがトラブル防止の基本。
抱っこの順番などは、両家に事前に伝えておくとスムーズです。
お宮参りに行かない人はどれくらいの割合ですか?
最近では、体調や天候、コロナ禍の影響などから「お宮参りに行かない」「写真撮影だけで済ませる」家庭も増えています。
おおよそ1割以上の家庭が参拝を省略しないと言われています。
無理をせず、家族に合った形でお祝いすれば大丈夫です。
引用・参照:スタジオ華縁ホームページ内ブログ
お宮参りの写真撮影はスタジオキャラットへ

お宮参りの記念撮影は、スタジオキャラットにおまかせください。
赤ちゃんのペースに合わせた丁寧な撮影で、泣き顔も笑顔もすべて大切な思い出として残します。
撮影をご利用いただいた方には祝い着のレンタルも無料でご用意しており、前撮りや後撮りの対応も可能です。
さらに、家族撮影や両家そろっての記念写真も経験豊富なスタッフがしっかりサポート。
「お宮参り 両家 トラブル」を避けたいママ・パパにも安心の撮影環境です。
一生に一度の大切な瞬間を、ぜひスタジオキャラットで残しましょう。
スタジオキャラットのお宮参り・百日祝い
まとめ
お宮参りは、赤ちゃんの健やかな成長を祈る家族の大切な節目です。
しかし、両家の価値観の違いから小さなすれ違いがトラブルに発展することもあります。
大切なのは「赤ちゃんが安心してお祝いできること」と「お互いを思いやる気持ち」。
夫婦が中心となって計画を立て、感謝の気持ちを忘れずに伝えることで、どの家庭も温かいお宮参りになります。
そして、その記念を写真に残すことが、家族の絆をさらに深める第一歩です。