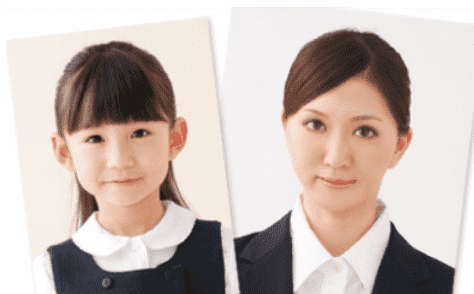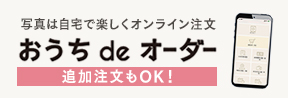お宮参りの意味・目的とは?場所や日程の決め方、当日の流れを解説

お宮参りは、赤ちゃんが生まれて初めて神社を訪れる伝統的な儀式で、日本の文化に深く根付いた行事です。新しい命の誕生を祝い、健やかな成長を願うために行われます。しかし、初めての行事で「いつ行うべき?」「服装はどうする?」と悩む方も多いのではないでしょうか。本記事では、お宮参りの意味や目的から、時期や当日の流れ、準備すべきポイントまで詳しく解説します。初めてのお宮参りを安心して迎えられるよう、ぜひ参考にしてください。
目次
お宮参りの意味・目的とは?
お宮参りは、生後間もない赤ちゃんの健やかな成長と健康を願う伝統行事です。地域や家族によって細かな慣習は異なるものの、赤ちゃんが初めて神社を訪れ、その土地を守る神様にご挨拶する重要なイベントとして行われます。
お宮参りの起源・歴史
お宮参りの起源は平安時代に遡り、赤ちゃん誕生の際に「産土神(うぶすながみ)」へ挨拶をする風習がルーツとされています。産土神はその土地の守護神であり、新しい命を守ると信じられてきました。室町時代には庶民にも広がり、江戸時代にはお宮参り後に親戚や知人を訪ね、誕生を報告する習慣も定着しました。
また、当時は出産を「穢れ」と捉える考えがあり、一定期間を過ぎて神社に参拝することは「忌明け」の意味もありました。赤ちゃんが氏子として地域社会に迎え入れられ、神様から祝福を受ける大切な通過儀礼でもあったのです。
お宮参りの概要(誰と何をするか)
お宮参りは、赤ちゃんが生後1か月頃を迎えた際に神社で祈願を受ける伝統行事です。両親や祖父母を中心に家族で参拝し、神主にご祈祷をお願いするのが一般的。赤ちゃんは祝い着を身につけ、昔は「父方の祖母」が抱くのが習わしでした。これは母親が出産後の忌明けを経ていないと考えられたためです。
ただし現代では、母親が抱いたり父親が抱いたりと、柔軟に選ばれるケースが増えています。参拝後には記念撮影や会食を行うことも多く、家族の絆を深める一日となります。
関連記事:
「お宮参りは何をするの? 準備からマナーや記念撮影までの基礎知識」
お宮参りの流れ【準備から当日まで】
お宮参りは次のステップで進めるとスムーズです。
- 1. 参加者の決定:両親・祖父母を中心に、誰が同行するかを話し合います。
- 2. 日程・場所の決定:赤ちゃんと母親の体調を第一に、神社やお寺を選びます。
- 3. 各種手配:ご祈祷の予約、初穂料の準備、写真館や食事会場の手配を済ませておきましょう。
- 4. 当日の参拝:祝い着や服装を整え、余裕を持って移動。ご祈祷・記念撮影・会食を流れに沿って行います。
事前準備を丁寧に行えば、当日は落ち着いて赤ちゃんとの特別なひとときを楽しめます。

お宮参りはいつ行う?時期の決め方と注意点
お宮参りの時期は地域によって異なりますが、一般的には生後30日~100日頃に行われます。男の子は31日目、女の子は32日目という慣習もありますが、現在は家族の予定や体調を優先するのが一般的です。
六曜(大安・仏滅など)を気にする必要はありませんが、ご両親や祖父母の希望を尊重すると安心です。また真夏や真冬は赤ちゃんに負担がかかるため、気候が厳しい時期を避ける配慮も大切です。涼しい時間帯を選ぶ、寒い日は防寒を徹底するなど工夫しましょう。
お宮参りの日取りの決め方と注意点
日程を決める際は以下のポイントを参考にしてください。
- 1.赤ちゃんと母親の体調を優先:産後間もない時期は体調が不安定なため、無理をしないスケジュールを心掛けましょう。
- 2.吉日を選ぶ:大安や友引など、縁起の良い日を選ぶのが一般的です。
- 3.家族の都合:祖父母や親戚も参加する場合、全員のスケジュールを調整します。
- 4.神社の混雑状況:希望する神社が特定の日に混み合う場合、事前予約を検討するのがおすすめです。秋の土日祝日は七五三で込み合う場合があるため、特に注意がひつようです。
また、六曜に加え「一粒万倍日」「天赦日」などの吉日を選ぶ方も増えています。気候や混雑状況も踏まえて、家族みんなが安心できる日を選びましょう。
関連記事
「お宮参りはいつする?日程の決め方や注意点を徹底解説」
お宮参りの時期はいつ?ずらす場合の注意点
お宮参りの時期は、地域や家庭の慣習により異なりますが、一般的には赤ちゃんが生後30日前後で行われることが多いです。ただし、この時期にこだわる必要はなく、さまざまな事情に応じて日程をずらすことが可能です。例えば、赤ちゃんや母親の体調が整っていない場合や、天候が悪い場合、また家族が揃いやすい日程を優先する場合など、状況に応じて柔軟に変更できます。特に近年では、家族のライフスタイルや仕事の都合を考慮して、土日祝日や赤ちゃんがもう少し成長した時期に実施する家庭も増えています。
また、夏の暑さや冬の寒さを避けるために気候の良い季節にずらすことも一般的です。
真夏や真冬は避け、過ごしやすい季節に行うのも安心です。
六曜や吉日を意識する場合は、大安以外にも天赦日や一粒万倍日などを選択肢に入れるとよいでしょう。
大切なのは「家族が無理なく参加できる日」であることです。お宮参りの本来の目的は赤ちゃんの健やかな成長を神様に祈ることですので、家族全員が安心して参拝できる日程を選ぶことが重要です。日程変更をする際は、事前に神社に相談し、予約を確保しておくとスムーズに進められます。家族が無理なく、心地よく祝える日を選び、赤ちゃんの健やかな成長を祈念する特別なひとときを迎えましょう。
お宮参りはどこでやる?場所の選び方と主な選択肢
お宮参りの場所選びでは「赤ちゃんと母親の体調を第一」に考えましょう。移動時間の短さや設備の充実度(授乳室・おむつ替えスペースの有無)も重要なポイントです。
以下に代表的な場所を3つ挙げ、それぞれの特徴を解説します。
産土神・氏神神社
産土神(うぶすながみ)とは、赤ちゃんが生まれた土地を守る神様のことです。一方、氏神(うじがみ)は、その地域の住民を守る神様を指します。お宮参りでは、赤ちゃんを地域の神様にお披露目し、健やかな成長を祈るため、産土神や氏神を祀る神社を選ぶことが一般的です。具体的な神社の場所は、自治体や地域の神社総代に問い合わせると教えてもらえる場合があります。産土神社や氏神神社でのお宮参りは、地元とのつながりを感じられるだけでなく、今後の七五三や厄除けでも訪れる機会が多くなります。
探し方としては、お住まいの地域の「神社庁ウェブサイト」で検索すると分かりやすいでしょう。
有名な神社・ご縁のある神社
お宮参りの場所として、有名な神社や家族に縁のある神社を選ぶ方もいます。有名な神社は格式が高く、多くの参拝者を集める場所が多いため、特別な雰囲気の中でお宮参りを行うことができます。たとえば、安産祈願で訪れた神社や、結婚式を挙げた神社を選ぶことで、家族にとってより思い入れの深い行事となります。ご縁のある神社でのお宮参りは、赤ちゃんの誕生を祝う気持ちとともに、家族の歴史を重ねる意味を持ちます。ただし、有名神社は格式があり特別感がありますが、移動時間や待ち時間が長くなる場合があります。赤ちゃんやママの負担を考え、無理のない範囲で選びましょう。
菩提寺・ご縁のあるお寺
家族の信仰や習慣に応じて、お宮参りを菩提寺や縁のあるお寺で行う場合もあります。菩提寺とは、先祖代々の墓があるお寺のことで、家族の歴史や精神的なつながりを感じられる場所です。また、特定の宗派や信仰を持つ家庭では、お寺での祈祷を選ぶことが一般的です。お寺では、赤ちゃんの健康や成長を祈願する儀式が神社とは異なる形式で行われますが、その意義は同じく赤ちゃんの未来を祝うものです。ご縁のあるお寺を選ぶことで、先祖とのつながりを意識し、家族の絆を深める機会となるでしょう。
お寺でのお宮参りは「初参式」などと呼ばれることがあり、祈祷の形式が神社とは異なります。謝礼は「お布施」として渡し、金額は5,000円〜10,000円が一般的。のし袋は「御布施」と表書きし、新札を用意すると丁寧です。家族の宗派や信仰に合わせ、事前に相談しておきましょう。

お宮参り当日の流れとタイムスケジュール例
お宮参り当日のスケジュールは、スムーズな進行のために事前に計画しておくことが大切です。以下は一般的な流れの一例です。
1.余裕を持ったスケジュールで準備・移動(約30分~1時間)
お宮参り当日は、赤ちゃんと家族の服装や持ち物を整え、忘れ物がないか確認しましょう。赤ちゃんの機嫌が良い時間帯を考慮し、早めに出発するのがポイントです。混雑を避けるため、神社やスタジオへの到着時間に余裕を持ったスケジュールを組むと安心です。
2.記念撮影はいつ、どこで撮る?(約1時間)
スタジオや神社近くの写真館で家族写真を撮影します。赤ちゃんの体調や機嫌を優先し、休憩を挟みながら進めましょう。記念写真はお宮参りの思い出として大切なものなので、プロに依頼することをおすすめします。写真撮影はお参りの後でもできますが、お参りの前に行う方が赤ちゃんやご家族の負担も少なく済みます。赤ちゃんの祝い着を写真スタジオでレンタルする場合は、着物を受け取ります。
3.神社でのご祈祷・参拝の流れとマナー(約30分~1時間)
記念撮影後、神社へ向かいご祈祷を受けます。事前予約をしておくとスムーズです。ご祈祷では、赤ちゃんの健やかな成長と家族の幸せを祈ります。混雑する場合もあるため、時間に余裕を持ちましょう。また、受付時に祈祷料(初穂料)を収めることが多いので、事前に準備しておきましょう。
4.食事会(約2時間)
お参りの後は、家族でお食事会を開きましょう。お店で行う場合は事前に予約しておくとスムーズに進行できます。赤ちゃんが泣いたり、授乳をする場合を考慮して個室のあるお店を選ぶと安心です。この機会に親族と赤ちゃんの誕生を祝うひとときを楽しんでください。
◆タイムスケジュール例
| 時間 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 8:00 | 自宅で準備 | 授乳・オムツ替えを済ませる |
| 9:00 | 神社または写真館へ移動 | 渋滞・休憩を考慮 |
| 10:00 | 記念撮影 | 赤ちゃんの機嫌が良い時間帯を優先 |
| 11:30 | ご祈祷・参拝 | 初穂料を準備して受付 |
| 13:00 | 食事会 | 授乳スペースの確認を |
| 15:00 | 帰宅 | 赤ちゃんを早めに休ませる |
当日の移動時間や赤ちゃんの体調を考慮し、余裕のあるスケジュールを心掛けてください。

お宮参りの服装はどうする?
お宮参りでは、赤ちゃんをはじめ家族全員がフォーマルな服装を心掛けることが重要です。それぞれの服装例を見ていきましょう。
赤ちゃんの服装例
赤ちゃんには伝統的な祝い着(掛け着)を着せることが一般的です。祝い着は赤ちゃんの着物に掛ける形で使用します。祝い着の下にはベビードレスやセレモニードレスを着せるのが一般的です。また、季節に合わせて赤ちゃんが快適に過ごせる素材やデザインを選ぶようにしましょう。
ママ・パパの服装例
ママはフォーマルなワンピースやスーツを選ぶのが一般的です。着物を着用する場合は訪問着や色無地がおすすめです。パパはスーツやジャケットスタイルで清潔感を意識しましょう。赤ちゃんを引き立てるようシンプルで格式を意識した上品な色味やデザインを選ぶと良いでしょう。
関連記事:「お宮参りの服装はどうするべき?マナー・ルールや選び方のポイントなどを徹底解説」
お宮参り前にやるべき準備リスト
お宮参りをスムーズに進めるためには、事前の準備が欠かせません。特に赤ちゃんを連れての外出は予想外のことも起きやすいので、余裕を持った準備を心がけましょう。
ご祈祷の予約と初穂料(謝礼)の準備
お宮参りでは、赤ちゃんの健やかな成長を祈るために神社でご祈祷を受けるのが一般的です。多くの神社ではご祈祷をスムーズに行うため、事前の予約を受け付けています。特に有名な神社や行事シーズンは混雑が予想されるため、早めに連絡をして希望の時間帯を確保しましょう。予約時には、赤ちゃんの名前や生年月日を尋ねられることがあるため、事前に情報を準備しておくと便利です。また、ご祈祷の際にお納めするのが「初穂料(はつほりょう)」です。一般的には5,000〜10,000円程度が目安。のし袋は紅白の蝶結びを使い、表書きは「御初穂料」または「御玉串料」と記します。新札を準備するとより丁寧です。渡す際は神職や受付の方に正面を向けて両手でお渡しするのが基本的なマナーです。準備を怠らず、当日を気持ちよく迎えられるようにしましょう。
関連記事:
【お宮参りで知っておきたい!】初穂料について徹底解説
記念写真の予約|スタジオ?出張撮影?
お宮参りの記念写真は、赤ちゃんの特別な日の思い出を形に残す大切なものです。撮影を希望する場合、事前に撮影スタジオや神社でのロケーション撮影を予約しておくことが必要です。特に週末や祝日は人気が集中するため、早めの予約が肝心です。撮影スタジオでは祝い着や小物がレンタルできる場合も多く、撮影時、赤ちゃんの衣装やごきょうだいの衣装も着用できるプランを選ぶこともできます。また、スタジオでの撮影後に神社に移動するスケジュールや、参拝後に神社の境内で記念撮影を行う場合の時間配分も考慮して計画を立てることが重要です。撮影場所やプランについては、事前に家族で話し合い、希望するスタイルを明確にしておくとスムーズです。撮影時に赤ちゃんがリラックスできるよう、休憩時間や授乳タイムを考慮したスケジュールを組むことも忘れないようにしましょう。
• スタジオ撮影のメリット:天候に左右されず、プロの設備で美しい仕上がりに。衣装レンタルが豊富。
• デメリット:移動が増える、撮影が時間制で慌ただしい場合も。
• 出張撮影のメリット:神社や自宅で自然な雰囲気を残せる。移動負担が少ない。
• デメリット:天候や撮影許可が必要なケースがある。
当日と別日で撮影する家庭も多くなっています。別日に行えば赤ちゃんや家族の負担が軽減され、表情も落ち着いた写真が残せるメリットがあり

食事会の手配・予約
お宮参りの後、食事会を開く家庭も多いですが、これは必須ではありません。家族の都合や予算、赤ちゃんの体調に応じて柔軟に判断しましょう。食事会は親族が集まり、赤ちゃんの誕生をお祝いする大切な時間となりますが、必ずしも外食や大規模な会食にこだわる必要はありません。
レストランやホテルを予約する場合、赤ちゃんが快適に過ごせる設備が整った場所を選ぶと安心です。個室や座敷があるお店、赤ちゃん用の椅子や授乳スペースを完備している施設がおすすめです。事前にメニューやサービス内容を確認し、参加者の人数やアレルギーにも配慮しましょう。
一方で、自宅で家族だけで簡単にお祝いする選択肢もあります。自宅なら赤ちゃんのペースに合わせられ、リラックスした雰囲気で過ごせます。ケータリングやテイクアウトを利用することで、準備や片付けの負担を減らすことも可能です。家族の状況に合わせて、無理のない形で赤ちゃんの誕生を祝うひとときを楽しんでください。
お宮参り当日の持ち物リスト【チェックリスト付き】
お宮参り当日は赤ちゃんと一緒に外出するため、必要な持ち物を事前にリストアップし、しっかり準備しておきましょう。まず、赤ちゃんのオムツ、授乳用のミルクや哺乳瓶、着替え、ガーゼハンカチなどの基本アイテムは必須です。天候に応じて赤ちゃんを保温するためのブランケットや日差しを避けるための帽子なども準備しておくと安心です。また、ご祈祷の際に必要な初穂料を封筒に入れて持参します。さらに、家族全員の衣装の手直しやメイク直しに使える小物類(ハンカチ、予備のストッキングなど)も用意しておくと便利です。カメラやスマートフォンも忘れずに持参し、神社の境内や家族の写真を残しましょう。移動中や待ち時間に赤ちゃんがリラックスできるおもちゃやお気に入りのアイテムを用意するのもおすすめです。当日慌てることがないよう、前日までにバッグにまとめておき、持ち物リストを再確認して万全の準備を整えましょう。
チェックリスト
赤ちゃん用
☐ オムツ・おしりふき
☐ 授乳用ミルク・哺乳瓶(母乳の場合は授乳ケープ)
☐ 着替え(肌着・洋服一式)
☐ ガーゼハンカチ
☐ おしゃぶり
☐ お気に入りのおもちゃ
☐ 抱っこ紐・ベビーカー
☐ ブランケットや帽子(季節に応じて)
衛生・便利グッズ
☐ ビニール袋(オムツや汚れ物用)
☐ タオル・ハンカチ
☐ 消毒用シート
家族用
☐ 初穂料(のし袋入り)
☐ ハンカチ・予備のストッキング・化粧直し用グッズ
☐ カメラ・スマートフォン(充電確認)
持ち物をカテゴリごとに分けてバッグに入れておくと、当日の準備がぐっと楽になります。
関連記事:「お宮参りの段取りと持ち物は?スタジオ撮影時の準備物あわせて解説」

お宮参りの記念撮影はどうする?おすすめの方法を紹介
お宮参りの記念撮影には、大きく分けて「スタジオ撮影」と「出張撮影」の2種類があります。
• スタジオ撮影は、天候に左右されず衣装や小物も揃っているため安心。きちんとした家族写真を残したい方に向いています。
• 出張撮影は、神社や自宅で自然な雰囲気を残せるのが魅力。赤ちゃんや家族がリラックスした表情を残したい方におすすめです。
ただし、出張撮影は天候や神社の撮影許可が必要な場合があるため事前確認が大切です。
お宮参りの写真撮影はスタジオキャラットへ
お宮参りの大切な思い出を写真に残すなら、プロの技術と豊富なプランが魅力の「スタジオキャラット」がおすすめです。お宮参り撮影をご利用いただいた方は撮影の前後1か月まで祝い着が1日レンタル無料になるサービスも行っています。また、豊富な祝い着や背景を活用した撮影はもちろん、家族全員の自然な笑顔を引き出す撮影にも定評があります。
まとめ
お宮参りは、赤ちゃんの健やかな成長を願うと同時に、家族の絆を深める大切な行事です。
• 起源や意味を理解することで、より意義深い一日に。
• 時期や日取りは赤ちゃんとお母さんの体調を第一に、柔軟に調整。
• 場所選びは移動距離や設備の有無も考慮すると安心。
• 当日は余裕あるスケジュールと事前準備でスムーズに進行。
• 記念撮影はスタジオ・出張撮影いずれもメリットがあり、家族に合った方法を選びましょう。
家族みんなで心地よく過ごせる日を選び、赤ちゃんの誕生をお祝いするひとときを大切にしてください。
再編集:2025年8月20日
スタジオキャラットのお宮参りプランはこちら