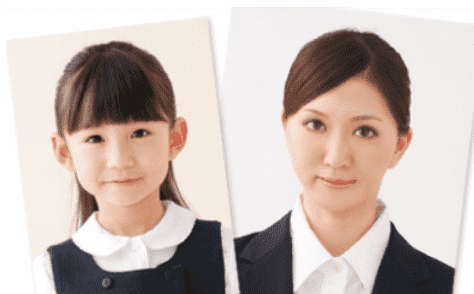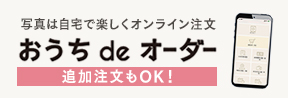七五三はいつ?【完全ガイド】年齢・お参り・写真撮影の最適な時期

七五三は、お子さまの健やかな成長を願い、神社に参拝してお祝いする日本の大切な行事です。3歳・5歳・7歳の節目を迎える年に行われることが多く、着物姿での記念撮影や、祖父母を交えた食事会など、家族の思い出づくりの機会にもなります。
とはいえ、「いつ参拝すればいい?」「数え年と満年齢どっちがいい?」など迷う方も多いはず。
本記事では年齢や参拝時期、写真撮影のベストタイミングまで、七五三の計画に役立つ情報をまとめてご紹介します。
目次
七五三とは?子供の成長を祝う日本の伝統行事
一般的に七五三は、お子さんが3歳・5歳・7歳になった年の11月15日に神社に参拝します。
これからの健やかな成長をお祈りし、無事にその年齢を迎えられたことを神様に感謝するのです。
11月15日に必ず参拝しなければならないわけではなく、ご家族の予定や天候に合わせて前後1〜2ヶ月の間に行う方も多いです。
近年では、神社参拝に加えて記念撮影やフォトスタジオでの撮影、家族や親戚との食事会をセットで行うケースも増えています。特に祖父母にとっても大切な日になるため、会食や写真撮影の場を通じて三世代での交流のきっかけにもなります。
なぜ七五三をお祝いするようになったの?
七五三の歴史は長く、由来は平安時代より伝わります。
医療が発達していなかった当時は「7歳までは神の子」という言葉があったほど、子どもが健康に成長することが難しいとされていました。
七五三のはじまりは、大切な我が子がいつまでも健康に成長して欲しいという願いを込めて、節目に神様に感謝したことであるといわれています。
七五三をお祝いする年齢は?数え年・満年齢や早生まれも解説
お祝いする年齢は、男の子と女の子で異なります。
• 3歳:男の子・女の子
• 5歳:男の子のみ
• 7歳:女の子のみ
これは由来となった儀式に基づいています。
• 髪置の儀(かみおきのぎ)…3歳の男女
• 袴着の儀(はかまぎのぎ)…5歳の男の子
• 帯解の儀(おびときのぎ)…7歳の女の子
年齢の数え方は以下の2種類があります。
• 数え年:生まれた時を1歳とし、元旦ごとに1歳加える
• 満年齢:生まれた時を0歳とし、誕生日ごとに1歳加える
昔は数え年が一般的でしたが、最近はどちらでも構いません。
数え年は満年齢より幼いため、体力的に不安な場合は満年齢で行う方も多いです。特にお参りと記念撮影を同日にしたい場合は、余裕を持てる満年齢がおすすめです。
早生まれの場合は、同学年のお子さんより満年齢で行うと1年遅くなります。成長や着物のサイズ感を考慮し、体力がついてから行う方も少なくありません。
年齢早見表(2025〜2026年版)
| 生まれ年 | 数え年での七五三 | 満年齢での七五三 |
|---|---|---|
| 2022年生 | 2024年(3歳) | 2025年(3歳) |
| 2020年生 | 2024年(5歳) | 2025年(5歳) |
| 2018年生 | 2024年(7歳) | 2025年(7歳) |
| 2023年生 | 2025年(3歳) | 2026年(3歳) |
| 2021年生 | 2025年(5歳) | 2026年(5歳) |
| 2019年生 | 2025年(7歳) | 2026年(7歳) |
七五三のお参りはいつがベスト?時期の決め方とポイント
七五三のお参りは必ず11月15日でなくても大丈夫です。
当日は神社が混雑し、待ち時間も長くなります。11月の週末や祝日も混みやすいため、落ち着いて参拝したいなら平日が狙い目です。
土日しか時間が取れない場合は、前後1〜2ヶ月にずらすのもおすすめです。
特に混雑を避けたい場合は…
• 10月:まだ気温が穏やかで、紅葉や秋晴れの中で撮影も楽しめる
• 12月上旬:七五三シーズンを過ぎて混雑が少なく、ゆっくり参拝できる
お子さんが着物を着る場合は、気温にも注意してください。高すぎると体調を崩す原因にもなります。
七五三のお参りに六曜は関係ある?気にする場合の選び方
昔から日本では冠婚葬祭において、六曜を意識します。
六曜とは、以下のものです。
- 大安(たいあん)
六曜の中で1番吉とされる日。「大いに安し」との意味合いを持つため、結婚式や結納などのお祝いごとを行う日に向いています。 - 先勝(さきがち、せんしょう)
午前中が吉、午後が凶の日です。先に行動するのが良いとされているので、お祝いごとは午前中に行うのがよいです。 - 先負(さきまけ、せんぶ)
午前中が凶、午後が吉の日。先に行動すると負けることを意味するため、物事を行う際は午後からはじめるとよいでしょう。 - 友引(ともびき)
朝は吉、昼は凶、夜は吉とされている日。友を引く意味があり、結婚式に向いている日です。しかし、友を冥土に引き込んでしまうため、この日は葬式には向いていません。 - 仏滅(ぶつめつ)
仏でさえも滅してしまうと言われる大凶日。お祝い事には不向きですが、悪縁を切って新しく何かを始める日としては適しています。 - 赤口(しゃっこう、しゃっく)
正午のみは吉とされ、他の時間帯は全て凶となります。仏滅と並ぶよくない日です。
六曜は冠婚葬祭で用いられる暦注ですが、神社の行事やご祈祷とは関係ありません。
日柄を気にする場合は「大安」や午前中の「先勝」、午後の「先負」など縁起の良い時間帯を選ぶと安心です。
ただし六曜にこだわりすぎて天候や家族の予定を犠牲にするより、「家族が揃ってお祝いできる日」を優先しましょう。
記念撮影のタイミング

七五三の撮影タイミングは大きく3つ。
• 前撮り
• お参り当日
• 後撮り
それぞれにメリット・デメリットがあります。
前撮り
前撮りは七五三よりも前の日程におこなう撮影です。
4〜10月頃に行われることが多く、余裕を持って撮影できます。
【メリット】
• 余裕を持って撮影できる
• お得なキャンペーンあり(例:撮影料割引・アルバム特典・兄弟衣装無料)
• 衣装レンタルを早めに予約可能
• 七五三当日のイメージづくりになる
• 日焼け前に撮影できる
• お子さまがさらに成長した姿を残せる
【デメリット】
• 人気スタジオは早めの予約必須
• 誕生日によっては着物が大きい場合あり
• 年賀状に間に合わないことも
スタジオ選びのポイントは、衣装の種類・撮影データやアルバムの料金プラン・兄弟撮影や家族写真の追加料金の有無など。
キャンペーンでレンタル料無料やアルバム割引がつくこともあります。
スタジオキャラットではお得な前撮りキャンペーンを実施しています。
お得な料金で利用できるプランや、人気のサービスがパックになったパックプラン、プレゼント特典など早い時期の撮影がお得です。ぜひキャンペーンをチェックしてくださいね。
「開催中の七五三キャンペーンはこちら」

お参り当日
七五三当日の参拝前にフォトスタジオにて記念撮影をします。
お参り当日のメリット・デメリットは以下のとおりです。
【メリット】
• 1日で記念撮影と七五三の参拝が完了する
• お着物など衣装を着るのが1回で済む
【デメリット】
• 撮影から参拝まで長時間になため、お子さんが疲れやすい
• 落ち着いて記念撮影できないこともある
• 衣装をたくさん着て撮影することが難しい
• 天候に左右される
• 食事会や移動時間も考慮が必要
当日に記念撮影も合わせて行うと、1日で全てが完了します。
忙しいご家庭には助かりますね。
お着替えが苦手なお子さんや、撮影時とお参り時、両方でお母さんが着物を着たい場合など着物を着る手間が1回で済みます。
しかし、ヘアメイク・着付けから記念撮影をし、神社への参拝はお子さんにとってもハードスケジュールとなり、神社での参拝でも、お子さんがぐずってしまうことも考えられます。
撮影の後に参拝に向かう場合は、時間の都合上落ち着いて記念撮影ができない可能性があり、参拝後の撮影ではお子さんが疲れて、いい表情が撮れないこともあります。また、ドレスなどの洋装での撮影を希望される場合も同様にお子さんの体力的に心配な面もあります。
疲れ対策として、撮影の合間に軽食や水分補給をし、移動中はベビーカーや抱っこで体力温存を。好きなおやつやおもちゃを持参してご機嫌を保つのも効果的です。
また、お参り当日の撮影は屋外撮影が多く、雨や強風、極端な暑さ・寒さで予定変更が必要になる場合があります。特に着物姿では天候の影響を受けやすく、快適さや仕上がりに差が出ます。
参拝・撮影後に食事会を予定する場合、移動や待ち時間で子どもが疲れやすくなります。スケジュールが詰まると笑顔が減ることもあり、余裕を持った計画が大切です。

後撮り
後撮りは、七五三のお祝いが終わった日以降や12月以降に撮影をします。
後撮りのメリット・デメリットは以下のとおりです。
【メリット】
• 衣装を選びやすい
• 夏に日焼けをしてしまっても時間がある
【デメリット】
• 体調管理が難しい時期である
• 撮影者対象のレンタル衣装特典が受けられない
七五三のシーズンが終わった後の12月中旬以降の記念撮影は、予約が混み合っていない時期であるため、選べる衣装の選択肢が多いのがメリットです。
夏に日焼けをしてしまっても、冬なら時間があるため日焼けが改善される見込みもあります。
フォトスタジオでは撮影者を対象にレンタル着物が借りられる特典があることがあります。その場合、撮影が後になると特典を受けられないことも。
また、冬場は風邪をひきやすく体調管理が難しい時期です。
後撮りをする場合は、体調にも気をつけて計画を立ててくださいね。
まとめ
七五三は、子どもの成長を祝う日本の大切な節目。参拝や記念撮影は必ず11月15日でなくても良く、家族の都合や体調を優先して決められます。前撮り・当日撮影・後撮りそれぞれにメリットがあるため、スケジュールや希望に合った方法を選びましょう。大切なのは、家族みんなでお子さんの成長を喜び合える時間を持つことです。
スタジオキャラットの七五三撮影はこちら
再編集:2025年8月20日