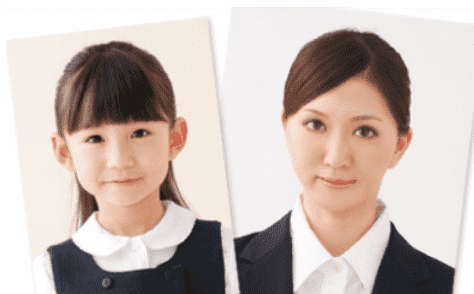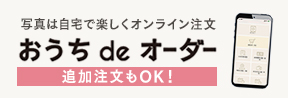七五三は何歳でお祝いする?【2025年版早見表】数え年・満年齢や祝う時期を解説

七五三は、子どもの健やかな成長を願う大切な行事。けれども「何歳で祝うの?」「数え年と満年齢、どちらが正しいの?」と迷うご家庭も多いはずです。
本記事では、2025年の七五三対象年齢をわかりやすく早見表にまとめ、数え年と満年齢の違いや、男の子・女の子の祝い年齢の意味、家族の事情に合わせた決め方まで丁寧に解説します。
目次
七五三の年齢の基本|数え年と満年齢の違いと計算方法
普段の生活のなかでは意識することが少ない「数え年」と「満年齢」。
一般的に年齢を聞かれて答えるのは、誕生日ごとに1歳加える「満年齢」です。
一方「数え年」は、生まれた日を1歳とし、毎年1月1日に一斉に年を取る数え方です。そのため、満年齢より1〜2歳大きくなる計算になります。
年齢の計算例
| 生年月日 | 満年齢の計算 | 数え年の計算 |
|---|---|---|
| 2022年10月生まれ | 2025年10月で3歳 | 2025年1月時点で4歳 |
| 2023年2月生まれ | 2025年2月で2歳 | 2025年1月時点で3歳 |
男の子と女の子の七五三年齢の違い
七五三は、男の子は3歳と5歳、女の子は3歳と7歳でお祝いするのが一般的です。
3歳は「髪置(かみおき)」といって、昔は赤ちゃんの産毛を剃る習慣を終える年。
5歳は「袴着(はかまぎ)」で初めて袴を身につける節目。
7歳は「帯解(おびとき)」で着物の付け紐を外し、本式の帯を結ぶようになる儀式に由来します。
近年は男の子も3歳でお祝いするご家庭が増えており、兄弟姉妹で一緒に写真を撮るケースも人気です。とくに3歳はまだあどけない可愛らしい姿を残せる貴重な時期。家族のライフスタイルや記念写真のタイミングに合わせて、柔軟に決める傾向が強まっています。
七五三は数え年?満年齢?メリット・デメリットと年齢の決め方

七五三は、数え年でも満年齢でもお祝いできます。
昔は数え年が主流でしたが、最近は子どもの成長に合わせて満年齢で行うご家庭が増えています。
男の子は3歳(希望すれば)・5歳、女の子は3歳・7歳で行うのが一般的です。
数え年で行うメリット・デメリット
【メリット】
• 伝統的な習慣に沿える
• 祖父母世代が理解しやすい
【デメリット】
• 実際の年齢より幼く、衣装や長時間の外出が負担になることも
満年齢で行うメリット・デメリット
【メリット】
• 成長しているため着物姿が映える
• 当日のスケジュールがこなしやすい
【デメリット】
• 祖父母が「遅い」と感じる場合がある
2025年〜2027年 七五三対象年齢早見表(満年齢ベース)
満年齢をベースに記載します
| お祝い年 | 3歳 | 5歳 | 7歳 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 2022年生 | 2020年生 | 2018年生 |
| 2026年 | 2023年生 | 2021年生 | 2019年生 |
| 2027年 | 2024年生 | 2022年生 | 2020年生 |

こんな場合はどうする?七五三の年齢に関するQ&A
Q1. 早生まれの子はどちらで祝うべき?
A. 現在は満年齢で行うのが主流です。特に3歳の場合は、春〜秋にかけてしっかり歩けるようになってからのほうが安心です。
Q2. 兄弟姉妹がいる場合は?
A. 年齢差が近ければ同じ年に合わせることも多いです。上の子が5歳・下の子が3歳というように同時撮影すると、衣装レンタルや写真代が節約できるメリットも。
Q3. 海外在住の場合は?
A. 現地で行う場合は秋の涼しい時期を選び、神社参拝の代わりに家族で感謝の時間を設けるのも良いでしょう。日本に一時帰国するタイミングで実施する家庭も多いです。
Q4. 人見知りや着物が苦手な子は?
A. 無理に年齢通りに行わず、子どもが落ち着いて参加できる年にずらしても問題ありません。
Q5. 天候や混雑を避けたい場合は?
A. 七五三の参拝は必ず11月15日でなくても大丈夫です。近年は混雑を避けて、9〜10月や12月初旬に行うご家庭も増えています。特に写真撮影は別日にスタジオで済ませ、参拝は家族だけで落ち着いて行うスタイルが人気です。
七五三の写真撮影はスタジオキャラットへ
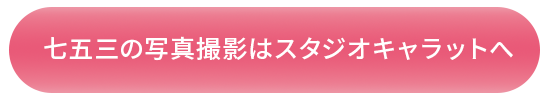
まとめ
七五三は、子どもの成長を祝う大切な節目ですが、数え年・満年齢のどちらでもお祝いできます。男の子は3歳(任意)と5歳、女の子は3歳と7歳が一般的。家族の予定や子どもの成長に合わせて、無理のないタイミングを選びましょう。早見表やQ&Aを参考に、思い出に残る七五三を計画してみてください。
再編集:2025年8月20日